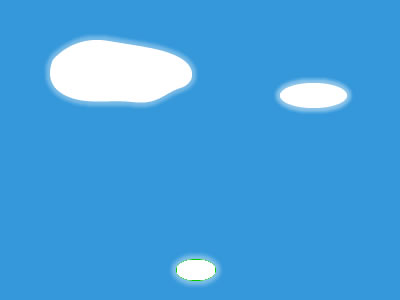「画用紙を黒くぬりつぶす子どもが描いていたのは?」、帯のコピーにひかれて絵本『まっくろ』を手にした。先生の「みんなの心に浮かんだことを描いてみましょう」の一声で、思い思いの絵を描きはじめた子どもたち。小学校の美術の教室風景から物語ははじまる。ひとりの少年が画用紙をまっくろにぬりつぶしている。おどろいて目をまるくする先生は「ちゃんとした絵を描きなさい」といわずもがなの一言を吐いてしまう。ちゃんとしたなんてどんな絵なのだろうか。だが、ぬりつぶすことに熱中する少年はそんな注意なんか馬耳東風、一枚の画用紙をまっくろにすると、二枚目、三枚目、四枚目をと同じように黒くぬりつづけるのだ。
一読して、ぼくは美術教育で知られる「キミ子方式」を想いおこした。80年代の後半、かつてH社の編集者であったころ、同僚が子どもたちと学ぶカラフルな絵画教育実践書『三原色の絵具箱』(松本キミ子/堀江晴美:共著)を制作中で、著者とともに子どもたちも参加する実践的な本づくりをしていた。これらスタッフの表情が充実して楽しそうに見えたのが記憶に残る。この絵画指導法は小中学校で美術教師だった松本キミ子が1970年代半ばに子どもたちにも描く楽しさを持たせたいと授業を展開する中で考え出された。構図や形から描きはじめ、そののちに色をぬっていくという従来の描き方は子どもたちには難しいらしく、描くのが苦手な子どもたちを生んでしまうらしい。
そこで、松本は考えた。赤・青・黄の三原色に白の4色の絵具があれば自然界のどんな色だって作りだせるのだから、まず描く対象の色を三色+白色で造りだす。そして、構図を考えてから描きはじめようなどと言わず、下描きもせず、輪郭線も描かず、はじめから絵具で描く。動物だったら鼻か口を描く起点として描き、つぎに、となりの部分を描く。となりを、となりをと描いていく。画用紙のサイズにあわせて描くこともしない。紙が足りなくなったらどんどんつぎたして、余ったら切ればいい。あとは想像力にまかせて自由に楽しみながら描くだけ。こうして、子どもたちは部分を描き上げるたびに、「絵が描ける」「絵を描いた」という達成感を獲得する。キミ子方式は仮設実験授業を提唱した科学教育研究者の板倉聖宜の評価を得て、以降、全国的に普及する飛躍的な広がりを見せた。
すっかり横道にそれてしまったが、なにかひとすじ、絵本『まっくろ』の少年と描き方で通底するところがあると思うのだがどうだろうか。
ページを何度となくめくっても、少年の画用紙をまっくろにぬりつぶすいきおいはおさまらない。果たして少年は何を考えているのか。ただただ黒くぬりつぶしているだけなのだろうか。
ここから物語は、ぐん、ぐーんと飛躍する。学校を終えても、家に帰っても、朝がきても、休みだって少年は画用紙に向かいまっくろにぬりつづけた。紙が足りなくなったらつぎたす。すでに数十枚から百枚に近づいた。まあ、こんな展開が現実なら、「この少年はいったいどうしたんだ。何かおかしいぞ」と、先生だけでなく、少年のともだちや、とうさん・かあさんに、じいちゃん・ばあちゃんも、みんなみんな心配になるだろう。
しかし、これが物語の意図する真骨頂なんだと、ぼくは思う。心配を裏がえせば痛快で面白いストーリーとなる。少年は周囲の心配なんか、なんのその。ぬりつぶす手をとめない。まっくろくろくろ、まっくろけと画用紙をつぎたしては黒くぬりつぶしていくのである。
ところが、つぎたしていく紙が数百枚に達するころ、黒くぬられていく画用紙に少しずつ白いスペースが見えるようになった。黒色は婉曲して描かれて白地はしだいにふえていく。体育館だろうか。少年の画用紙が一堂に広げられた。そこにはなんと、とてつもなく大きなくじらの姿があらわれたではないか。
……少年は、まっくろにぬりつぶしてなんかいなかったのである。少年は、こころに浮かんだくじらを脳裏に映し出し、黒い部分から部分へと描きつづけていたのだった。大きくて丸味のある胴体にやさしい目の描かれたくじらの絵は、あたたかい親しみを感じさせる大作品となったのである。
この作品、大人の常識をはるかに超える想像力や発想力をもつ子どもたちの感性をうばわないようにと訴える公益社団公共広告機構の全国キャンペーン「IMAGINATION/WHALE」から生まれた作品である。その意を絵本は実現したのではないだろうか。(おび・ただす)