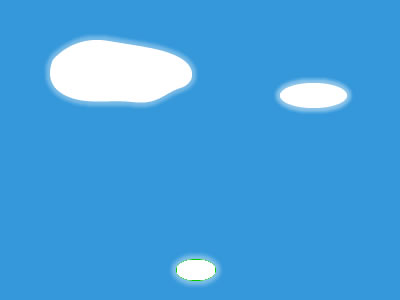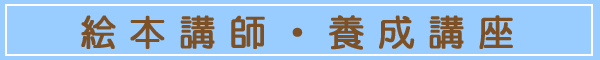

第18期「絵本講師・養成講座」大阪会場
第18期「絵本講師・養成講座」大阪会場第5編 2021年12月18日(土)

報告者 多本 ゆき枝

第18期「絵本講師・養成講座」大阪会場第5編が2021年12月18日(土)、CⅠⅤⅠ研修センター新大阪東で開催されました。真冬の寒さになった日、新型コロナウイルス感染予防対策をした会場には静かな緊張感が漂い、加藤美帆さん(芦屋3期)の司会で講座が始まりました。

午前の部は、森ゆり子理事長による絵本講座実演「絵本で子育て」です。対象を保育園児の保護者と設定し、『ちびゴリラのちびちび』(ほるぷ出版)の読み聞かせから始まりました。子どもは読んでもらいながら絵のことばを読み取ります。「子どもに届ける本だからこそ本物を」という画家・赤羽末吉氏のことばを紹介され、「よい絵本」を子どもに届けましょうと語られました。
自尊感情は誰かと共に作るものであり、いつも見守ってくれる人がいる安心があってこそ自分は大切な存在だと認識できる。絵本の読み聞かせは、子どもに愛を伝える5つの方法「ことば」「スキンシップ」「時間共有」「プレゼント」「求めることに応える」の全てを満たしている。忙しくても一日3分でいいから、絵本を読み聞かせることで子どもに愛を伝えてほしいと話されました。
「子どもは今日感じたことを明日頭で理解する」と言うように、人との温かいふれあいの中で感動しながら覚えることばが深い思考を支え、人格を高めていく。心を揺さぶることで心の基礎体力がつき、心の核を作り、自分の考えを持つ大人に育つ。『わたしのいもうと』や『さっちゃんのまほうのて』を紹介していただきましたが、大人のわたしも心を揺さぶられました。読み手の思いと絵本自体が伝えてくれる感動を会場の皆で共有した時間でした。
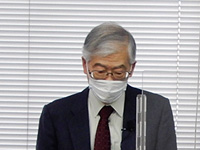
午後の部は、片岡直樹氏の講演「テレビ・ビデオ・スマホが子どもの心を破壊している」です。順調に成長している乳幼児が電子メディアに長時間接触することで、目を合わさず表情が乏しくなり、ことばが遅れる症例を数多く紹介してくださいました。近代IT革命と子どもの育ち方は逆相関にある。生まれた時にはみんな白紙状態であり、赤ちゃんの神経回路は親がつくるもので、親子のスキンシップや外での五感を使った遊びが大切だと力説されました。そして、話ことばは親子間の応答的環境下で自然に出てくるものであり、早くから読み書きことばを教えてはいけないと話されました。
子どもの育ちには、勤労体験(お手伝い)、挫折・困難体験、欠乏体験が不可欠である。大人はすぐに手伝ったり先回りしたりしてしまうが、子どものときから小さな失敗体験を積み重ねるほど豊かに成長する。失敗しても大人が大騒ぎしなければ、子どもは二度と同じことはしないのだから、放っておくことが大切だということです。

大長咲子副理事長(芦屋1期)から最終課題リポートの書き方の説明があった後は、お待ちかねのグループワーク。講演内容や最終課題について活発に意見交換がなされ、終了時刻まで楽し気な話し声が響いていました。
次回は閉講式です。きっと皆さん晴れやかな笑顔で臨まれることでしょう。
(たもと・ゆきえ)
![]() 過去の「絵本講師・養成講座」の各編はここからご覧いただけます。
過去の「絵本講師・養成講座」の各編はここからご覧いただけます。