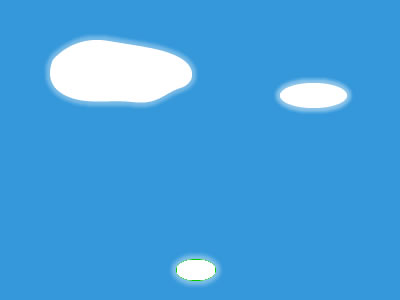大阪会場第2編 読み聞かせについて 2019年6月22日
報告者 芦屋6期 大西 徳子

家庭の中にどれほど言葉があるかが問われてる
第16期「絵本講師・養成講座」(大阪会場)が2019年4月20日、春らしい陽気に包まれた新大阪CIVI研修センターにて開講。早くから到着された受講生の期待と緊張感が徐々にお部屋に満ちての開講式となりました。

第16期「絵本講師・養成講座」(大阪会場第2編)が2019年6月22日(土)、CIVI研修センター新大阪東において開催されました。
午前の部は、松居 直先生(児童文学者)の「絵本のよろこび」(DVD講義です)。
子どもたちが大きくなったとき、日本の社会がどうなっていくか? これからどういう風に生きていったらいいのか、大人が深く考えなければいけない時代が来ています。20世紀は「お金」と「物」の時代で、経済は拡大したが言葉の力が失われてきています。
わたしの生きた時代は、母親の子守唄やわらべ唄を耳から聴き、言葉の温かさは無意識の裡(うち)にこころに残っています。戦時中でも言葉が不思議なファンタジーの世界に連れて行ってくれました。
サン=テグジュペリ作の『星の王子さま』は、人間にとって「大切なものは目に見えない」ことを教えてくれました。言葉も時間も、愛も悲しみも、嘘も見えないが、言葉を通して大切なものが目に見えるように子どもを育てていかなければいけない、と話されました。

お昼休みをはさみ、午後の部は、とよたかずひこ氏(絵本作家)の講演から始まりました。
紙芝居『はい、タッチ』(脚本・絵 とよた・かずひこ)の誕生に纏(まつ)わる、野球少年とのエピソードなど、あたたかい気持ちになりました。
絵本ができるまでの仕組みのお話の中で、もう一回読んでという期待に応えて、繰り返し読んでもらえる本、読み聞かせをする大人が面白がる絵本作りが大切だと話されました。現在、おじいちゃんが孫に読んであげる絵本の制作を考えておられるそうです(楽しみですね)。とよた氏の講演の時間は、とても会場が優しい雰囲気に包まれました。

その後、大長咲子副理事長からスクーリングの学習要領の説明、課題リポートの質問に対しての回答がありました。
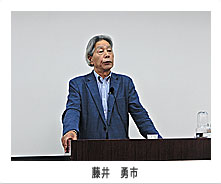
続いて藤井勇市専任講師から、「本講座ではグループの入れ替えや、他のグループワークの討議内容の発表はしません」と話されました。また、集団での特定・不特定多数の読み聞かせの場においても、「家庭で子どもや孫に読んでほしい」と伝えることが大切です。そして、学校などのボランティアについては、「絵本は言葉や心を伝えるもので教えるものではない。強制を含む授業(教育)の前に子どもの心を解放してあげることが大切」と説明されました。

続いて、課題の『いない いない ばあ』を熊懐賀代さん(芦屋4期)が読みました。そのあと、それぞれにご自分の世界の『いない いない ばあ』をグループワークの皆さんに読み聞かせをし、絵本を読んでもらう心地よさを実感しあいました。
課題終了後は、次回の打ち合わせなどを積極的に意見交換されていました。第2編で受講生の皆さんがとても打ち解けて絵本のお話に花が咲いているのを傍聴し絵本の力を感じました。
(おおにし・のりこ)
会場風景