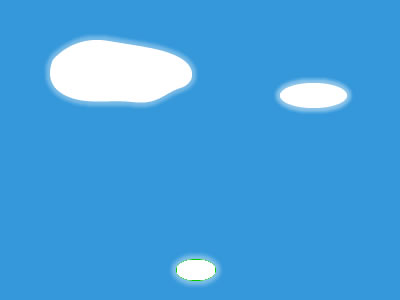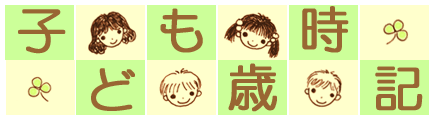(モーリス・ドリュオン/作、安東次男/訳、岩波書店)
庭仕事で考えたこと
吉澤 志津江
単年度雇用の身分となって休みが増え、庭仕事を楽しんでいる。花々の、高さや時期、色合いなどを考えて植え替え、敷石で通路を作る。何がどこに植わっているのか、芽が出てみないと分からなかった究極のナチュラルガーデンが、わずかずつでも変わっていくのは張り合いだ。が、新しく植えた球根や苗が花を咲かせてくれるのとは対照的に、いつの間にか絶えてしまったものもある。二年ほど前まで咲いていたミヤコワスレが芽を出さず、結局、苗を購入して少しずつでも増えてくれたらと願いながら植えつけた。こんなときには「チトのようなゆびがほしい」としみじみ思う。
『みどりのゆび』((モーリス・ドリュオン/作、安東次男/訳、岩波書店)の主人公チトは、指を触れるだけで花を咲かせることができる八歳の少年だ。庭師のムスターシュじいさんは、チトが“みどりのおやゆび”の持ち主だということを見抜いて、チトの指南役となる。
チトは、刑務所や貧民街などに行って指を押し付けては、町を花で満たしていく。しまいには、武器工場に忍び込んで、工場のあらゆるところに親指を押し付ける。その武器を購入した二国間の戦争は、なんと花を浴びせ合う花合戦になって、ただちに平和条約が結ばれる。ムスターシュじいさんに「これほどすばらしい仕事をするとは」とほめられて、チトは心を熱くする。
物語の最後でチトがなにものだったのか明かされるが、なによりもチトは八歳の子どもだった。
「毎日安心して寝て、安心して起きることはとてもうれしい」(5月7日付信濃毎日新聞朝刊)。ウクライナから県内に避難してきている八歳の男の子の言葉だ。谷川俊太郎さんは『せんそうしない』(講談社)で、《せんそうするのは おとなとおとな》と書く。大人には、子どもの幸せな育ちを保障する役割があるはずなのに、役割を果たすどころではない。ウクライナでは、ロシア軍によって、子どもの命まで奪う所業が繰り返されている。
これは一人の為政者がやっていることなのではない。日本にも同じような時代があったのではなかったか。反戦を表明しただけで拷問を受けて亡くなった人もいる。その時代に生きる大人の、ひとりひとりの責任がそこにある。ハンナ・アーレントの “悪の凡庸さ”の概念を知れば、自分も、いとも簡単に為政者側につく人間となりうることへの恐れを抱くはずだ。
エゴン・マチーセンの『さるのオズワルド』(こぐま社)は、言葉遊びが楽しい絵本だが、本質は深い。ちっちゃなさるのオズワルドは、いばりやのボスざるに、きっぱりと「いやだ!」という。
たった一人でもオズワルドになれるのか自分に問いかけながら、ウクライナのひまわり畑を思って、今日も草を引く。
(よしざわ・しづえ)