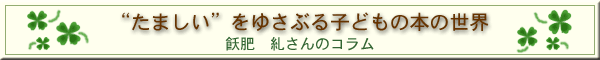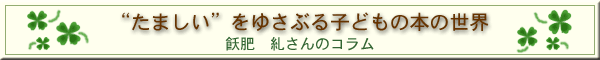|
「絵本フォーラム」第98号・2015.01.10
●●88
何処にでもいそうなじいさんの振る舞い。
天才だって、その才は凡たる人格からしか生まれない。
『ピカソはぼくの親友なんだ』(六耀社)
 今回もじいさんと子どもの交流話。じいさんは子どもたちとどんな関係を持てるのか、例えば「ともだち」になることができるのだろうか、とあれこれ考えてみる。さて、相手が幼児ならまだしも学童ともなるとじいさんはもう体力で勝てない。そして今風の遊戯などちんぷんかんぷんだ。ところで、じいさんは関係を持ちたいのかどうか。いったい子どもが好きか。そして、子どもたちはどうだろう。じいさんをどう思っているのだろうか。好きか嫌いか。 今回もじいさんと子どもの交流話。じいさんは子どもたちとどんな関係を持てるのか、例えば「ともだち」になることができるのだろうか、とあれこれ考えてみる。さて、相手が幼児ならまだしも学童ともなるとじいさんはもう体力で勝てない。そして今風の遊戯などちんぷんかんぷんだ。ところで、じいさんは関係を持ちたいのかどうか。いったい子どもが好きか。そして、子どもたちはどうだろう。じいさんをどう思っているのだろうか。好きか嫌いか。
公園で遊ぶ子どもたちの喚声がうるさいと怒る大人たちが増えているという。その大人たちの中にじいさんの顔ものぞく。登下校途上の子どもたちに怒声をあびせる輩までいる。現代社会の病巣がとりわけ都市生活者の心中に鬱屈して巣食い瘤のような塊となる。ときに破裂する。深く進行する嫌な世の中。厄介な時代だ。
もとより子どもは天真爛漫な存在。大人たちに暫しの喜びを与えてくれる存在なのである。子どもたちの一挙手一投足にじいさんは目を奪われ、そのたびに淀んだ澱が落ちる。気分は晴れる。
例えば、多くを子どもに遊んでもらうぼくの場合。それだけで無条件に愉快な気分になる。じいさんは子どもたちと相性がいい、と思いたい。
今回紹介する一筋縄ではいきそうもないじいさんも、何だか可愛らしいほどに子どもと融和する。お相手の子どもはまず、「ぼくのともだち」と一対の位置に立って、じいさんからつまらない虚飾を剥ぎ取ってしまう。じいさんも、晴れてまったきの「ともだち」となる。
この爺さんの名は、パブロ・ピカソ。みなさん周知のあのピカソだ。
はてさて、みなさんは、ピカソのことをどれほど知っているか。美術史上の傑出した画家でブラックとともにキュビスムの創始者であり、本人でも言い間違うほどのとんでもない長い本名を持つ。結構な艶福家で二度の結婚に幾人かの愛人もいた。「ゲルニカ」に代表される反戦絵画を描くフランス共産党員だったとか…。なにしろ実話の豊かさも多彩な逸話の多い天才画家だった。
このピカソが古稀にさしかかったころ訪れたイギリスの知人家族にトニー少年がいた。彼がピカソの「ともだち」となる。で、後年成人したトニーが写真家だった母親撮影の写真を構成して絵本化したのが『ピカソはぼくの親友なんだ』である。
絵本はトニーとピカソの交流日記といった趣だが、そこかしこに、ピカソの凄味と何処にでもいそうなじいさんの振る舞いがよく描かれて興味を走らせる。天才だって、その才は凡たる人格からしか生まれないのだ、と見て取れるのがうれしい。
ピカソはトニーの母親の顔を描く。絵は正面を向き歯を見せて笑っている。ところが右頬のへりをなぞると母親の横顔ラインが不思議なほどに正しく重なるではないか。ピカソ美術館をはじめ欧州各地でピカソの描く絵画の相当数を鑑賞してきたぼくは驚かない。ピカソのデッサンの凄さは語るまでもない。ただ、キュビスム絵画の見方のひとつがこんなところにあったのかと感心する。
ウシやバッタや、ウマにニワトリと動物好きのピカソとトニーのふたり。それこそウマがあって親友となった。興に乗って興奮しピカソに咬みつくトニー。なんのこれしきとばかり手加減せずに咬みつき返すピカソ。親友とはこんなふうでありたいなぁ。じいさんとか子どもとか、そんな関わりを超えた「ともだち」関係。あるのは友情のみと絵本の著者トニーは、言いたいようだ。
何処にでもありそうなガラクタを利用して創作される彫刻や焼き物の他、ピカソの数々の絵画・彫刻作品が割合無造作に収載構成されるこの絵本は、まるで「小さなピカソ美術館」のようでもある。日本語版のテキスト文字の扱いがぼくには気になるが、読後感に気分の良い一味が残る作品である。
(『ピカソはぼくの親友なんだ』(六耀社))
|