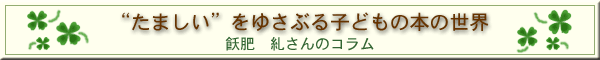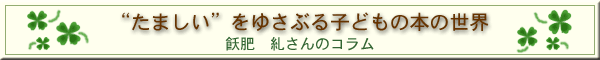「絵本フォーラム」第50号・2007.01.10
●●39
「けち」な大人の心性と 子どもの純なひたむきさ
『ろくべえ まってろよ』
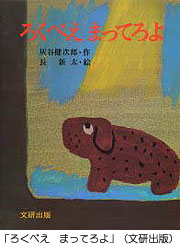
犬がわが家の一員となって 25 年になる。小学生時の娘と息子が原っぱで見つけ連れ帰ったのが真っ白の牡犬マルで老衰により 13 年の人生 ( 犬生 ? ) を完うした。真っ黒の牝犬ハッピーは成人した娘が友人宅から貰い受ける。娘も息子も結婚して家を離れ、現在 12 歳のハッピーは初老の夫婦ふたりと生きる。
犬の面倒を見るのは結構大変だ。家人が旅することも容易でない。なにより近隣に迷惑かけないかと気が揉める。そんな厄介さを抱えても、いったん家族の一員に迎えると愛情が湧く。よその犬となれば話は別だ。人間扱いはしないし、犬は犬。うるさければ追い立てるし怖ければ避ける。その程度でその場かぎりの感情しか持てないのが大人ではないか。
だが、子どもたちはちがう。明らかにちがう。友だちを気遣うように犬に対しても同じように気遣う。小さな生き物の命にみずみずしい感受性を示す子どもたちに対して大人たちは気恥ずかしくなるはずだ。
灰谷健次郎と長新太が『ろくべえ まってろよ』で描き出すのはそんな子どもたちだ。暗くて深い穴に落ちたろくべえ。俊敏さが犬の特性なのにマヌケな犬。だから、かんちゃんもろくべえを「まぬけ」と言う。だが、かんちゃんの「まぬけ」は親友のドジに“何てことをしたんだよ。大変じゃないか”の意が滲んでいるとぼくは汲みとる。子どもたちはみな一年生で大好きなろくべえの一大事に救けに乗り出すのである。
「ろくべえ。がんばれ」とみんなが叫ぶ。しかし、励ますだけではどうにもならないことを子どもたちは知る。ろくべえだってそうだろう。「そう言ったって何をがんばるの?」といった思いだろうか。大人たちはこんな無意味な言葉をときおり子どもに投げかけるが、聞かされるほうはたまったものではないと思う。
で、子どもたちは対策会議。まず、お母さんらを連れてくるがろくろく相手にしてくれない。かんちゃんは「けち」と口ごたえ。「ぼくがおりていく」というのに「許しません。穴の底にはガスが溜まっていて死ぬ事だってある」とお母さんは怖い顔をするのだ。なおのこと早く救けてやらないと拙いじゃないか。この「けち」な大人たちメ。
♪ドングリコロコロ…、おもちゃのチャチャチャ…♪、子どもたちは歌を唄い出すがろくべえは目を少し開けるだけ。ろくべえの好きなシャボン玉を吹いても、ろくべえはピクリとも動かない。そこへゴルフのクラブを持ったおじさんが来るが、「大変だな。犬でよかったな」と言っただけ。…大人なんか、まったくあてにできないと悟ったのか、口をきゅっと結んだ子どもたちは頭が痛くなるほど考えるではないか。かんちゃんが「クッキーを篭の中に入れて下ろしたら…」と突然叫んだ。ろくべえの恋人・クッキーを乗せた篭を下ろせばろくべえは喜んで乗るはずだというのである。名案ではないか、子どもたちはすごい。そろり、そろり。篭を下ろすと二匹の犬はひとしきり戯れたのち無事に篭に乗る。…かくして、ろくべえの救出作戦は大成功となる。
話は、真っ暗な穴だけが舞台。子どもたちがろくべえを穴から救いだすというシンプルな物語。だけど、ぼくの読後に残る不思議な感動は嫉妬にも似る複雑な感情となる。大人たちの不甲斐なさと子どもたちの小さな命を救おうとするひたむきさがあまりにも際立って、“なるほど”と簡単に頷くわけにはいかないのである。
子どもたちの息づかいまで聞こえそうな八度も繰りかえす「そろり、そろり。」の読点と句点の憎いまでの文体。子どもの純朴な心を精緻に捉える灰谷健次郎の目がすごいとぼくは思う。そして、子どもたちの揺れ動く表情や、ろくべえの諦観したようすを強く優しく描く長新太の絵づくりに感服する。4見開き頁を縦に展開して暗い穴の深さを示す画面構成には、“さすが!”の一言しか吐けないではないか。
児童書界の巨魁ふたりは昨年あいついで天国へと逝った。ぼくらにとって残念としか言いようがない。だが、傑作は読み継がれてゆくだろう。 |