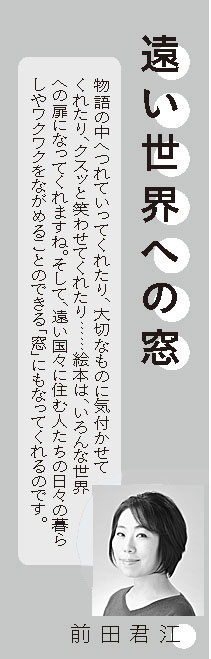新連載
遠い世界への窓
第12回の絵本
『わたしの足は車いす』

『わたしの足は車いす』(フランツ=ヨ-ゼフ・ファイニク/作、ヴェレ-ナ・バルハウス/絵、ささき たづこ/訳、あかね書房 )
小学校四年生になる娘が、学校の「総合」の学習で、障がいをもつ人たちについて調べることになりました。授業の方法や内容はよく分からなかったのですが、脳に障がいをもつ人、先天的あるいは後天的な理由で手や足を動かせない人のことを各自で調べているようでした。
どんな問題にも関心をもつことは素晴らしいのですが、私が閉口したのは、娘が、覚えたての「肢体不自由」という言葉を日常生活でも使いたがるようになってしまったこと。電車やファミレスで車いすに乗った人を見かけると、「ママ、あの人は、肢体不自由だよ」、「あの人は知能障がいだよ」。
医療や行政でそうしたラベリングが必要なことはあるかもしれないけれど、車いすに乗った通りすがりのその人だって、きっと好きな食べものがあって、好きなアイドルや芸能人がいたりして、「こんにちは」と言ったら、「こんにちは」と返してくれるフツーの人にちがいないのに……。
こんなことを考えていたときに出会ったのが、『わたしの足は車いす』でした。この絵本のステキなところは、何よりもまず、表紙の軽やかなオレンジ色! なんだか踊りだしたくなるような軽やかな色です。
主人公の女の子、アンナは、両足が動かないので、朝、目が覚めても、「いそいで起きるのは、にがて」です。動かない足をひとつずつ、両手でもちあげてから、くつ下をはきます。同じようにして、ズボンに足を通してから、車いすに乗って、台所へ行きます。車いすに乗ったまま、冷蔵庫からバターやミルクを出してお手伝いするアンナですが、この日アンナは初めて、おかあさんに頼まれます。「あとで、ひとりで、おつかいにいってくれるかしら?」
アンナはもちろん、「だいじょうぶ。やってみるわ」と答えて、どきどきしながら出かけていきます。広場で男の子たちが、ひとりの子を「やーい、でぶっちょ。おまえには、こんなこと、できないだろ」と、からかっているのを聞いて腹をたてたり、アンナをじろじろ見る人たちのことを「どうしてそんなにわたしを見るの」と気にしたり、アンナの目と心は、休むことなく、くるくると動いていきます。
絵本を読んでいる私まで、「まったくもう、大人ってどうしてこうなのかしら?!」といつの間にか、いっしょに腹を立てていました。大人って、ホント分かってない! 小さな女の子がアンナの車いすを指さして、「それ、なあに?」と話しかけてくれて、「これは、車いすって、いうのよ」とアンナがやさしく教えてあげようとしているのに、「そんなこと聞くもんじゃありません」と女の子を連れて行ってしまうお母さん。アンナがスーパーで棚から自分で取ろうとしたミルクやリンゴを、さっと取ってしまって手渡してくれる店員さん。ああ、もう、これじゃあ、はじめてのおつかいが台無し!
そんなアンナにも、ピンチはありました。横断歩道をぶじに渡りきったのはよかったけれど、歩道のふちが高くて、車いすでは上がることができません。信号も赤に変わってしまいました。巨人のように描かれた大人たちは、だれもアンナのことを見むきもしません。肝心なときに、何にもしてくれないんだから! アンナを助けてくれたのは、さっき広場でからかわれていた男の子ジニーでした。
ジニーとアンナの帰り道は痛快です。スーパーで買ったキャンディーを片手に車いすでくるくる回って、老夫婦をびっくりさせたり、さっきの小さな女の子と一緒に、車いすで思いきり走ったり!
私たちは、いくつも文化を持ったり、いくつもの体を持ったりすることはできないけれど、絵本のなかでは、アンナといっしょに笑って腹を立てて、アンナといっしょに車いすに乗ることだってできるんです。
原作者のフランツ=ヨーゼフ・ファイニクさんは、子どものころの予防接種の副作用で両足が麻痺し、以来ずっと、車いすでの生活。オーストリアの国家議員で「自分で人生を決めよう」運動のリーダーでもあります(絵本の原作者プロフィールより)。
(まえだ・きみえ)