 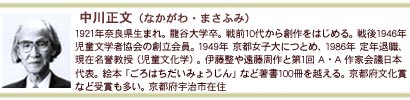 |
|
− 9 − この命、あなたならどうする |
|
金子みすゞは誰もが知っているように、昭和5年、ひとり娘を残して自死してから半世紀のあいだ、忘れられていました。そして行方がわからなかった手帳に清書された五百篇を超える童謡が発見されることによって、あっという間に今わが国で一ばん読まれて感動を与えている詩人になりました。 二十歳のとき初めて雑誌に採用された「お魚」は次のとおりです。 海の魚はかはいさう。 お米は人につくられる、 牛は牧場で飼はれてる、 鯉もお池で麩を貰ふ。 けれどもその魚は、誰からも世話にならない上、いたずら一つしないにかかわらず。こうして私に食べられてしまうのです。「ほんとに魚はかわいそう」 この詩は私たちの胸を、なぜこんなに打つのでしょう。それは魚じしん、誰からもかえりみられず一生懸命に生きています。にもかかわらず逆に私が食べてしまう。それは誰もが気がつきながら、みすゞと同じように平気で魚のいのちを奪う私たちの胸に、ぐさりと突きささるからです。 また「大漁」という代表作の詩も同じです。 漁師たちは朝はやくから沖にでかけて、イワシを山のようにとって戻ってきます。浜は豊漁景気でお祭りさわぎです。私たちは、そういうことがあることをよく承知しています。けれどもお祭り騒ぎをしている一方海の中では、捕らえられた仲間のイワシたちのために葬式をしているのではないか。それに気がついたみすゞは、はっとなるのです。 こういう詩を読むと、人は自分のことを棚にあげて、魚をかわいそうに思いながら、なぜ食べようとするか。また仲間を失った悲しみに気づきながら、一歩ふみだして、そういう自分をどう考えているか。 一応は非常にけわしい生きものの悲しみに胸をいためながら、みすゞと同じく自分の矛盾、生きるということの非合理性につきあたって、どうしていいか、どう考えていいか、みすゞと共に、こみあげてくる「生きるということの悲しみ」を思い知らされるのです。 みすゞの詩を読みながら、知っていながら知らないふりをしてきた自分。何とか解決しなければと思いながら、みすゞと胸をいためるより外ない自分がわかってくるでしょう。 私たちは多くの生きものの命を食べることによって、自分の命をささえてきました。食事を始めるときに最初に手をあわせ「いただきます」というのは、魚をはじめ命を私たちのために提供する生きものたちへの「おわび」の形でしょうか。 いま各地で子どもたちに「いのちの大切さ」を改めて認識させる教育が展開されています。コンビニでパックされている肉や魚が私たちの食材であって、それが、どういう経路を通って、ここまで運ばれてきたかを実際にわかってもらうために、ある高校ではニワトリをヒヨコのときから育てあげ、それが成長した暁には、生徒自身が解体して食膳にあげるという経験。生徒たちは一生忘れることのできないことだと一様にショックを受けていたと述懐していますが。私たちのまわりにある命の存在を、又これほど切実に考えたことはない、と語っておりました。 高校生は、こういう体験を通して、はじめて成人になるようですが、みすゞの絵本はどうでしょうか。考えてみると、非常に深刻それ自体のような詩を、見開き二頁ぐらいの絵本にして充分なのでしょう。 「お魚」や「大漁」クラスの童謡は、それ自体で一冊の絵本ほどに展開しなければ詩人の深い思いが言葉だけに終って、単に情緒的に「かわいそう」で終わってしまいそうですから、むつかしい問題です。安易に絵本化することのむつかしさが気になります。 その点、みすゞの作品ではたとえば題材が「木」や「芝草」レベルのものなら結構、恰好がつくと思いますが…。 |
「絵本フォーラム」43号・2005.11.10
前へ★次へ
