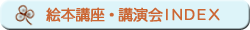|
| 本を読んでいますか? |
 皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。今、読書が人間の成長においてとても大切なものであるとわかっていながら、それが非常に困難な時代になっているような気がしてなりません。最初に、皆さんにリラックスしていただく意味も含めて、読書に関係する三つの質問をさせていただきたいと思います。 第1問。『坊ちゃん』『それから』『彼岸過迄』などを書いた有名な作家で夏目漱石という人がいます。この夏目漱石はまだ生きているか、それとももう死んでいるか。まだ生きているという方は、手を挙げてみてください。……いらっしゃいませんね。では全員、夏目漱石はもう死んでいて、この世にはいないということですね。 では、第2問です。山口瞳という作家がいます。山口瞳は男であるという方は、手を挙げてみてください。……半分ぐらいですね。では、山口瞳は女性であるという方は、手を挙げてみてください。……いらっしゃいませんね。どちらにも挙げなかった方もいらっしゃいますけれど(笑)。 では、第3問、最後の質問です。これは当地(山形)にちなんでの質問です。山形県東根市の特産はサクランボ、桜桃ですが、『桜桃』という小説を書いたのは誰かわかる人は手を挙げてみてください。……はい、ありがとうございます。 この質問を20代の方にさせていただくと、第1問、夏目漱石についての質問の正解率は80%です。答えは当然、「死んでいる」なのですが、「生きている」と答える方が20%いらっしゃいます。皆さんは全員正解でしたね。第2問、山口瞳は男なのですが、この正解率は50%です。最後の質問、『桜桃』の作者は太宰治ですね。これはこちらが初めての質問ですから、正解率は今のとおりです。 この質問の正解率を見ても、今、人が文学からどれだけ遠く離れているのかがわかります。とりわけ若い人が日本の近代文学、現代文学を読まなくなってから、相当な月日が経つのではないでしょうか。夏目漱石を読んでいればいい、山口瞳は男だとわかっていればいいということを言っているのではありません。私たちから文学がだんだん遠ざかっていくような社会になってしまっていることが、とても問題なのではないかと思っているのです。 |
| 大人になっても思い出せる温かなもの |
|
ちょっと50年ぐらい前の思い出話をさせていただきたいと思います。私が小学校1年生になったころのことです。大学を卒業したばかりの女性の先生が新しく赴任してこられ、私たちのクラスの担任になられました。その先生が、毎朝10〜15分ずつ、10日ほどかけて、ジュール・ベルヌの『十五少年漂流記』を読んでくださいました。『十五少年漂流記』というのは、15人の少年が乗り込んだ帆船が嵐によって海を漂流し、孤島に流れ着くのですが、そこでブリアンという少年をリーダーに、力を合わせて様々な困難に立ち向かうというお話です。でも、そういうお話の中身より、当時の私にとってうれしかったのは、毎朝毎朝、若く美しい女の先生に、優しい声で本を読んでもらえるということでした。 小学校1年生ですから、早く家に帰ります。うちは農家をしておりましたので、そのときそのときの季節に応じた農作業があります。私も学校から帰ると、その農作業を手伝っていました。しかし、私の心の中は、「早く明日が来てくれないか」という思いでいっぱいでした。夕ご飯を食べるのも、もどかしかったほどです。早く先生に会いたい。ブリアンはどうしただろうか、あの船はどうなっただろうか、島ではどんなことが起こるのだろうかという話の続きも気になりましたが、それよりも「先生に読んでほしい。あの優しい声に浸りたい」という気持ちが強かったのです。  それは当時の私にとって、とても楽しい時間でした。50年経った今も、鮮やかにそのときの情景を思い浮かべることができます。
それは当時の私にとって、とても楽しい時間でした。50年経った今も、鮮やかにそのときの情景を思い浮かべることができます。このような、学校における先生と子どもたちとのかかわり、あるいは家庭の中でのお父さん、お母さんと子どもたちとのかかわりというものが、現在の社会の中では、ほとんどと言っていいほどなくなってしまいました。これは、いたずらに皆さんを責めているのではなく、社会全体の構造がそうなってしまったということが当然あるわけです。しかし、その流れに流されてしまって、先生と生徒、親と子の濃密な関係がどんどん少なくなっているのではないでしょうか。これは、子どもたちにとって非常に不幸なことだと感じています。 もう一度繰り返して言いますが、『十五少年漂流記』という物語のハラハラ、ドキドキ、ワクワクした体験よりも、先生と共有できた時間のあたたかさ、喜び、うれしさのほうが、私の頭の中に鮮やかによみがえるのです。現在、こういう人間の関係がなくなってしまい、子どもたちは大変厳しい生き方を強いられているのではないでしょうか。表面的に見れば、社会は50年前よりもはるかに豊かになり、もはや「我慢する」ということもなくなりました。着るもの、住むところ、食べるもの、何もかもが豊かになりました。しかし、その豊かさの影に隠れて、人間同士のつながりが失われつつあるということを、やはりこの時期、我々大人が考えなければいけないのではないかと思います。 |
| なくなってしまった3つの“間”そして、手間 |
今日は30〜40代の方が大半だと聞きましたが、そのぐらいの世代の方が育ってこられた生活環境は、私たちの時代とは大きく違っています。生まれたときから、家にはテレビがあり、冷蔵庫があり、クーラーがあり、車がありました。このテレビというものがくせ者なのです。テレビ全般が悪いということではありませんが、子どもが小さいころからテレビを長時間視聴させると、その発育におびただしい障害が出る、異変が起こるということが様々なところで発表されています。生まれたときから「あるのが当然」という状態で過ごされた皆さんが、テレビのことについて真剣に考えてみるという機会はなかったと思います。「便利なものだ」「おもしろい」「いろいろな情報が簡単に手に入る」、そのような感覚で過ごされてきたのではないでしょうか。 皆さんにとって少し有利なことは、テレビはありましたが、まだ地域の友だちや仲良しグループなどと一緒に勉強したり遊んだり旅行したりする体験があったことです。つまり、あまり強い絆で結ばれていなかったとしても、「仲間」という関係がまだ存在していたと思います。ところが、今はそれがなくなりました。
皆さんにとって少し有利なことは、テレビはありましたが、まだ地域の友だちや仲良しグループなどと一緒に勉強したり遊んだり旅行したりする体験があったことです。つまり、あまり強い絆で結ばれていなかったとしても、「仲間」という関係がまだ存在していたと思います。ところが、今はそれがなくなりました。それを専門家の方たちは、三つの“間”が欠落していると言います。まず、今言っていたような「仲間」です。それから、みんなが群れて遊ぶための「空間」がなくなりました。それからもう一つ、今の子どもたちが大変な目にあっているのは、「時間」がないということです。学校が終わればすぐに、塾に行かなければいけない、おけいこに行かなければいけない。本来子どもが子どもとして獲得しなければいけない、あるいは経験しなければいけない“子どもの時間”が、親の勝手で奪われてしまっているのです。子どもは、自ら望んで塾に行きたいとは思っていないはずです。なぜ行かせるかというと、仲間が欲しいからということが多いと思います。当然、賢くしたい、勉強させたいという方もいらっしゃるでしょう。しかし、「どこかに子どもをやっておかなければ、昔存在した仲間の関係というものがなくなってしまう。今、それは塾ではないか。だったら、そこにうちの子も行かせよう」という方も多いのです。 かつて普通のものとしてあった「仲間」「空間」「時間」が、現在の子育ての現場から根こそぎなくなってしまっており、そこで皆さんは子育てをしていらっしゃるのです。大変なご苦労、大変なハンディキャップを背負いながら子育てをしているということになります。 そして最近、子育てにおいてもう一つの“間”が失われたと言われています。それは「手間」です。もう少し違う言葉で言うと、「手塩にかける」ということです。「子どもを手塩にかけて育てなさい」などと言うと、今の20代のお母さんたちは、「おにぎりをつくればいいのですか」と言われます(笑)。「手塩にかける」という言葉は、20代ではすでに死語なのです。 余談ですが、今、私が「シゴ」と言ったら、皆さんは頭の中でその発音を「死語」と漢字に変換なさっているはずです。しかし、20代では、皆さんが変換されたような言葉にならない方が多いのです。一番多いのは「私語」です。ひそひそ話。「『手塩にかける』という言葉は、今やひそひそ話になっています」(笑)。全く意味が通らないのですが、頭の中でそのように変換されてしまう方が多いのです。さすがに30〜40代の方は、そんなことはないと思いますが、今や「手塩にかける」という言葉は死語であり、その「死語」という言葉さえ変換できない方が多いのです。そういう中での子育ては、並大抵のことではありません。まさに察するに余りあります。 少しオーバーに言っているのではないかとお思いになったら困りますので、つい最近の新聞記事を持ってきました。長男にものを食べさせないで餓死させた母親をめぐる裁判の記事です。検察官は、その母親に懲役3年の論告求刑をしました。裁判官は、保護観察つきではありますが、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決の理由は、「被告には子育てをする能力がないばかりでなく、子育てを学べる環境にもなかった。長男の死は、被告1人だけの責任ではない」というものでした。一方、検察側は、「被告は長男がやせていることに気づきながら、男性とのデートにうつつを抜かし、餓死させた。その犯行は極めて悪質である」と指摘しました。 |
| 出発点は、読み聞かせ |
|
ここに現在の子育ての問題が象徴的に表れています。子どもを殺したお母さんは、子育てをする能力がない。能力がない人間に罪を問うのはおかしい。さらに裁判官は、「乳幼児を保護すべき母の行動として覚えなければいけない様々なことについて、実母の家出、養父による暴力などがあり、全く学ぶ機会がなかった」と言っています。 子育ての現場は今、ここまで大変な状態になっているのです。皆さんは、「これは親ではない」とおっしゃるでしょう。私もそう思いたいです。しかし現実には、こういう事件が起こっているのです。しかも、少しずつ起こっているのではありません。これにたぐいすることは無数の家庭の中で起こっており、たまたま死に至らしめるまでにはいかなかったという事例がたくさんあるのです。そういう子育ての現実の中で、皆さんは子育てをしていらっしゃるのです。 昔、我々の時代にも、確かにこういう事件はありました。しかし、比較的少なかったです。社会の構造が違いました。子育ては自分1人の力でしなければならないという社会ではなかったのです。「子育てには、村中の人の力が必要だ」。これはアフリカのことわざですが、当時の社会にはそういう意識がありました。年長者が小さな子どもを見て、「○○さんちの○○くんだ」ということをちゃんと言えるような地域があったのです。そういう地域がなくなってしまい、全部、自分が抱え込まなければならなくなってしまいました。東根市には、おじいさん、おばあさんがいらっしゃるご家庭も多いかと思いますが、日本の現在の家庭は、“お父さん・お母さん・子ども”という核家族がほとんどで、おじいさん、おばあさんなどは同居しないというところで子育てがなされています。子どもを育てるのは自分1人の責任、つまり、子育ては「私」だけでしなければならないという社会なのです。 ずいぶん前置きが長くなりましたが、本題に入りたいと思います。そういう社会状況の中での子育てにおいて、何が大事なのかということです。一つは、最初に言いましたように、先生と生徒、親と子、つまり人間と人間の心がつながる時間を、日常生活の中にどれだけ確保できるかということです。そしてもう一つは、その出発点となるものが読書ではないかということです。 |
| 人間が人間であるために |
|
先ほど、文学が人々から遠ざかっていると言いました。今、日常的に読書をしている人は極めて少なくなっています。このごろ新聞社が嘆いているのは、若い夫婦が家庭を持って、マンションやアパートに入っても、新聞を取らなくなってきたそうです。つまり、新聞まで読めなくなってしまっているのです。あるいは、読まなくても、その日その日が何の不思議もなく過ごせてしまう方が増えているのです。40〜50代の人は、1日新聞を読まなければ、何か忘れ物をしているように感じるかもしれません。しかし、今の20〜30代の方は、今日、どんな記事が載っていようが構わないのです。新聞を取っていなくても、インターネットで主要な記事を全部見ることができます。新聞でさえそういう状況ですから、ましてや本を買うなどという人は減っていく一方です。「今、あの本が売れているから、ちょっと読んでみたいな」と思って書店に買いに行く人が、極端に減ってきているのです。若い人たちの活字に対する接触度合いが減少の一途をたどっている時代なのです。このことによって今、何が起こっているのでしょうか。 本日の講演のタイトルは「心をはぐくむ読書」です。これを敷衍すれば、読書しない人は心がはぐくまれない、感情が豊かになれないということです。読書する行為とは、他人のつらさや痛み、強さや弱さなどを理解する心です。そして、人生は1回きりですが、いろいろな小説を読むことによって、いくつもの人生を体験することができます。もう一つ大事なことは、読書する営みは、人間が人間であろうとする行為だということです。読書をせずに、テレビやパソコンやゲームばかりをしていると、だんだん人間が人間でなくなって壊れてしまいます。 今、我々には想像もできないような事件が、若い人たちによって引き起こされていますが、それは実は不思議でも何でもありません。本を読まない人間は人の心がわからないのですから、人がびっくりするような事件を起こすことも、当人にとってはごく平気なことなのです。そう考えると、先ほどの長男を餓死させたお母さんのことだって、よく理解できます。そして、このまま行けば、確実にますますそういう人が増えていくことでしょう。 読書する行為、それはものを考える行為です。自分はどう生きればいいのか、物事をどうとらえればいいのかということを考えさせてくれる営みにほかなりません。ですから、読書を中断するということは、心が中断してしまうということなのです。 生まれたときから本に親しんでいない人が、ある日突然、本を好きになるということは、絶対にないなどとは言いませんが、ほとんどありません。「本って楽しいんだよ。ワクワク、ドキドキするんだよ。楽しいことも、おもしろいことも、うれしいことも、悲しいことも、いっぱい詰まっているんだよ」ということを体験させていない子どもが、中学生、高校生になって本を読むことはほとんどありません。例外はありますが、それは極端に少数です。小学校に上がる前、そして、小学校の1年生から6年生までの間が、子どもを本好きにする最大のチャンスなのです。本好きに育った子どもはきっと、自分が好きなもの、なりたいもの、やりたいことなど、目標や希望を心の内側に芽生えさせることができます。読書という体験にほとんど触れることなく育った子どもは、そうはなりません。そういう子どもが増えてきているから、怖いのです。 |
| あったかいお母さんのひざ、重くなっていたわが子 |
|
こういうことがありました。ある女性の先生の話なのですが、小学校3年生を担任したとき、なかなか授業ができなかったそうです。世に言われる学級崩壊の状態で、先生が話していても、なかなか子どもたちが聞いてくれないとのことで、私どものほうにお電話をいただきました。「実は私のクラスがこういう状態なのですが、どうしたらいいでしょうか。そちらは絵本の読み聞かせをすればいいとおっしゃっていますが、あれは本当ですか」というご質問をいただき、「では、まず2カ月か3カ月、毎朝、本を読んであげたらどうでしょうか。毎日1冊ずつで結構です。長いものは2日に分けても結構です」とお答えしました。 先生は、それを実行されました。すると、だんだん子どもが自分の授業を聞いてくれるようになり、半年後には、一緒に勉強ができる状態になったそうです。 そのとき、先生は子どもたちに一つの宿題を出したそうです。「皆さん、今日帰ったら、お母さんにひざに抱っこしてもらい、本を読んでもらってきなさい」という宿題です。でも、小学校3年生、ちょうど子どもから大人になる時期の子どもたちです。やっぱり照れがあって、なかなかお母さんに「抱っこして」とは言えません。明くる日、先生が「お母さんに抱っこしてもらって、本を読んでもらいましたか」と聞いたら、それでも7割の子どもたちが「はい」と言ったのです。「お母さんのひざはあたたかかった」「とても柔らかくて気持ちよかった」「絵本が楽しかった」という感想とともに……。 先生は、次の週も同じ宿題を出しました。そうすると、残りの3割の子どもたちも、してもらった子どもたちの感想を聞いていますから、全員、宿題をしてきたのです。  そして先生は、そのときの感想をお母さんたちにも聞いてみました。お母さんはどう言われたと思いますか。小学校3年生の子を抱っこしてあげることは、なかなかありませんよね。抱っこしてみたお母さんたちの感想は、このようなものでした。「うちの子はこんなに重くなったのね」「こんなに大きくなったのね」「すごく感動しました」
そして先生は、そのときの感想をお母さんたちにも聞いてみました。お母さんはどう言われたと思いますか。小学校3年生の子を抱っこしてあげることは、なかなかありませんよね。抱っこしてみたお母さんたちの感想は、このようなものでした。「うちの子はこんなに重くなったのね」「こんなに大きくなったのね」「すごく感動しました」これは、とてもいい宿題だと思います。お母さんたちの言葉が見事に、子どもを抱きかかえるその愛情を表現しています。ここに大事なことがあるのではないかと思うのです。 絵本を読む、読書をするということにおいて、大人は成果を求めたがります。「これだけの本を読んだのだから、それに応じただけの学力がつかなければいけない」と考えられるお母さん、お父さんが意外と多いのです。しかし、それは間違いです。子どもは、自分のために本を読んでくれる、抱っこをしてくれる、同じ時間を共有できるということにこそ、感動するものなのです。 一番悪い読み聞かせとは、読んだ後で「何が書いてあった?」「あのクマさんはどうしたの?」などと子どもに聞くことです。そんなことを聞く必要は全くありません。すばらしい絵と文章で書かれた絵本を、親が子に読んであげる。それだけで子どもの心は、いっぱいの満足を得ています。そして、その内容もちゃんと理解しているのです。読み聞かせの後に何か質問をしてしまうと、子どもは「絵本を読んでもらうことは、何かを質問されることだ」と思ってしまいます。そういう頭があったら、たとえ絵本を読んでもらっても、子どもは素直に親の心の中に入っていけなくなるのです。子どもにとって読み聞かせは義務になってしまい、楽しさが半減するどころか、何もなくなってしまいます。そういう関係では、読み聞かせは成立しないのです。 |
| 心がつくられる時 |
お母さんやお父さん、学校の先生など、読み聞かせをしていらっしゃる方、また、これから始めようと思っていらっしゃる方から、よく次のような質問を受けます。「怖い場面では、怖そうな声で読まなければいけないのでしょうか」「楽しい場面では、はしゃいだ声で読まなければいけないのでしょうか」。そういう読み方をしなければいけないと言われる方もいらっしゃいます。しかし、家庭や学校での読み聞かせにおいて、そういうことは全く関係ありません。普段の自分の声色、自分のペースで読んであげればいいと思います。 ただ、ツンツンした読み方をされたら、聞くほうはおもしろくないですよね。ですから、少なくともやさしく穏やかな気持ちで読んであげてください。方言まじりでも大丈夫。読みにくければ、詰まりながらでも大丈夫。そんなことは全く関係ありません。絵本を読み聞かせるときの大人は、教師でも俳優でもなく、子どもが素直に心を通わせ合える存在そのものです。人と人とが心を通じ合わせ、時間を共有することこそが、子どもにとって宝物になるのです。
ただ、ツンツンした読み方をされたら、聞くほうはおもしろくないですよね。ですから、少なくともやさしく穏やかな気持ちで読んであげてください。方言まじりでも大丈夫。読みにくければ、詰まりながらでも大丈夫。そんなことは全く関係ありません。絵本を読み聞かせるときの大人は、教師でも俳優でもなく、子どもが素直に心を通わせ合える存在そのものです。人と人とが心を通じ合わせ、時間を共有することこそが、子どもにとって宝物になるのです。読み聞かせの方法については、いろいろなところでいろいろなことが言われていますが、私に言わせると、間違いが多くて困るという感じです。ただし、付け加えて言っておきますと、大人たちが集まって絵本を材料に、「ここはこういう読み方がいいんじゃないかしら」「こういう読み方をしたら、子どもの受けがよかったですよ」と、研究してみることはいくらやってもいいと思います。しかし、子どもと心を通じ合わせ、時間を共有する読み聞かせについては、そういうものは全く必要ありません。ただ素直に、愛情を込めて読んであげればいいのです。ですから、誰でもできます。お父さんやお母さんはもちろん、おじいさんやおばあさんだってできるのです。 今のおじいさん、おばあさんで、昔話を空で言える方は多くありませんから、やはり絵本を読んであげるのがいいでしょう。我々の世代は、絵本が家の中にたくさんある時代ではありませんでした。私の家にも、絵本なんてほとんどありませんでした。そして、父や母は農家の厳しい労働で明け暮れていましたので、おばあさんが私をおんぶして、「かちかち山」や「花咲かじじい」、「一寸法師」などのお話をしてくれていました。ですから、「一寸法師」がどんな物語か、私は今でも鮮やかに思い出すことができます。内容を覚えていることがいいと言っているのではありません。おばあさんのあたたかさに包まれながら、心から安心してやさしい言葉に聞き入る。そういう体験が心をつくっているのだということなのです。それが読み聞かせではないでしょうか。 |