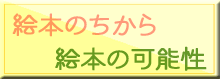 |
「絵本フォーラム」65号・2009.07.10 |
|
きつねが消えた? |
|
表紙の絵と題名が伝えるその絵本の力を、私なりにじっくりと確かめたい。そんな気持ちが働くらしい。  届いた絵本、中川正文/文、伊藤秀男/画『きつねやぶのまんけはん』の表紙と向き合う。大きな目と四角い顔、ひげの濃い野性味たっぷりのおっちゃんが、まず当然目に入ってくる。首のうすあずき色の襟巻きは伊達だが、それがちょっと短かめでいまいちの感は否めない。けれどそれはそれ。そこがまた、まんけはんらしいおっちゃんの人柄なのかも知れない。ざん切り頭だから、時代は明治より後だろうし、にこにこ顔のキツネの群れとおっちゃんの心の距離の近さからすると、大正・昭和でもあるまい。時は明治の前半というところか。 届いた絵本、中川正文/文、伊藤秀男/画『きつねやぶのまんけはん』の表紙と向き合う。大きな目と四角い顔、ひげの濃い野性味たっぷりのおっちゃんが、まず当然目に入ってくる。首のうすあずき色の襟巻きは伊達だが、それがちょっと短かめでいまいちの感は否めない。けれどそれはそれ。そこがまた、まんけはんらしいおっちゃんの人柄なのかも知れない。ざん切り頭だから、時代は明治より後だろうし、にこにこ顔のキツネの群れとおっちゃんの心の距離の近さからすると、大正・昭和でもあるまい。時は明治の前半というところか。
それにしても、「まんけはん」とはなんとふしぎな響きを持ったことばだろう。「はん」とつくので、人の呼び名であるのは間違いない。関西方言に疎い私にはその微妙なことばの味はわからない。でも、きつねやぶという設定もあってだろうが、京ことばや大阪弁とは違う土臭さと素朴さの上に、ちょっととぼけたユーモアさえ感じる。舞台は京都・奈良周辺の里山に続く村だろうか。私などは人の名前を聞くとまず漢字に直してみる。そうしないとイメージがつかめないし、憶えることもできない。ところがこの「まんけはん」は、そうした私の名前漢字化癖に、余計なことをするなとそっぽを向ける。方言の魅力なのだろう。「まんけはん」はそのまま「きつねやぶのまんけはん」なのだ。 秋も深く、落葉に敷きつめられて、あたりは抜けるように明るい。いかつい姿のおっちゃんだが、キツネとこんなに仲がいいのだ。それによく見ると、眼がぱっちりなのはいま風にいうと意外とかわいい。少なくとも悪いおっちゃんではなさそうだ。 さて、表紙をめくる。と、扉の絵は小屋いっぱいのニワトリ。表紙の変にうれしそうな顔のキツネたちとこのニワトリ小屋とを見れば、もういやでも事件は起きる。物語のお膳立てはととのった。さぁて、お立ち合い、というわけだ。 次への期待でページを進めることになる。 いわずもがなのことかも知れないが、絵本のなかには、本文中の一部を切り取って表紙の絵にしたものも多い。それが物語の山場部分であったりもする。どういうつもりの絵本作りかは知らないが、私は肝心な場面まで読み進めてきて、その手の作品におしなべてああ二番煎じだと思う。表表紙から裏表紙まで。どこも欠かすことのできない、一貫した物語のたいせつな場面として作られている、この『きつねやぶのまんけはん』は、やはりうれしい。 そして、それが作品世界に深みやゆたかさを醸し出してみごとなのだ。 まず主人公のまんけはん。村人とは違い山のキツネたちとは、つうかあの仲である。まんけはんのすること一つひとつが、どうも自分たちとは違ってキツネの肩を持つと、村人には見えていたのだろう。家も多分山寄りにある。だから豆腐屋のせいやんは、直接罪科のないことが分かっていても、ことキツネのいたずらは差し当りまんけはんに文句を、ということになる。まんけはんもまんけはんで、「なんでわしが……」とぶつくさいいながらも、キツネたちのことはやはり多少の責任はあろうと、懲らしめのために腰を上げる。いろいろな意味で山のキツネと村人との境界にまんけはんはいる。そのまんけはんの立場が、彼の性格・行動を特徴づけ、物語の葛藤・展開の深さの鍵となっている。 境界性については、場所についてもいえる。物語の山場は、キツネ穴とその周辺にある。宴会もキツネ穴の前で開かれる。秋ももう遅く(これもまた秋と冬の境界)、なにもわざわざ山のなかで開くこともあるまい、という向きもあるだろう。しかし、せいやんの早呑み込みであらぬ罪を着せられたキツネたちに詫びるには、どうしても彼らの住みかの前でなければならない。村人みんなが風邪をひくぐらいの罰は当然である。なお村人の風邪のその後は、いつにかかってキツネやまんけはんへのかかわり方にあって、さらに罰は重くなるかも知れない。なにしろ“風邪は万病の元”なのだから。もちろん、境界の人まんけはんに罰が当るはずもない。   その外にもあるこの作品の境界性については、ここでは省略する。ただ物語の発生や人間の魂の在り様にとって、境界が今でも欠くことのできない重要な領域であることは、指摘しておきたい。 その外にもあるこの作品の境界性については、ここでは省略する。ただ物語の発生や人間の魂の在り様にとって、境界が今でも欠くことのできない重要な領域であることは、指摘しておきたい。
もう一点。表表紙にいたなんとも楽し気なキツネの群れは、扉から以後ぷっつりと姿を消す。物語それ自体も、大人たちの右往左往に終始してキツネは姿を見せない。最終二場面の片隅と裏表紙に登場するだけである。絵本を開き始めて、やがて村人とキツネとの民話的交流の物語に発展するのかとの私の予想に反して、世話物風暮らしのリアリズムに徹する。ユニークである。しかし、それにしても、それぞれにやけた人間臭い表情のキツネたちは、いったいなんだ。作者は無駄なこと・意味のないものは描かないという。気になる。そんなとき、別件で理事長の森さんと電話で話した。電話のなかで「キツネは子どもたちですね」と森さんから聞いた。(ああ、やっぱり)と思った。それは当初うすうす感じていたのだが、リアリズム作品という私の思い込みに拘束されて、キツネと子どもとを重ねることにためらいがあった。リアリズムの視点からみると、気になることが全くないわけではない。トリが自分から出た小屋とキツネに襲われた小屋とは、なかの様子がまるで違う。人物描写の楽しく的確なこと、遠景でとらえた透明な夜景の美しいこと、物語を確かに語る絵はゆたかだ。でも、そんなことも実は気になっていたのだ。物語そのものの細部にも私なりにそれはあった。けれども森さんの話で、多くの部分はそれが消えた。 それにしても、「絵本で子育て」センターは、すぐれた創作絵本を直接子どもに手渡すという、新しい創造的活動に一歩踏み出した。今までの絵本の渡して育成に加えて、車の両輪ができたことになる。長い念願が実ったことでもある。この作品がより多くの子どもや大人の手元に届くよう自分なりに動いていきたいと思うし、こうした有意義な活動の最末端に、あるいはいるのかも知れない私自身をうれしいとも思っている。(いながき・ゆういち) <プロフィール > |
|
前へ ★ 次へ
